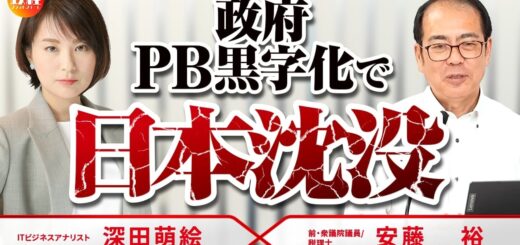雇用専門家が指摘『転職でキャリアアップは殆ど無理!?』 欧米型ライフワークバランスはマスゴミの幻想です! 海老原嗣生氏 #479

【目次】
00:00 1.オープニング
00:41 2.ジョブ型採用とスキルベース採用
05.44 3.硬直的な尺度で採用を行う事の問題点
08:37 4.ちぐはぐな給与体系
13:22 5.仕事事情は業界によって全然異なる
14:47 6.都市によって給与格差は異なる
15:38 7.リスキリングの様なバズワードに飛び付くのは辞めよう
17:17 8.反省できる人は生き残れる
(深田)
皆さん、こんにちは。政経プラットフォーム プロデューサーの深田萌絵です。今回は、雇用ジャーナリストの海老原嗣生先生にお越しいただきました。海老原先生、よろしくお願いいたします。
(海老原)
よろしくお願いします。今回は、私のど真ん中のテーマですね。
(深田)
そうです。テーマは『ジョブ型雇用はもう古い!スキルベース雇用で求められる「スキルテック」人材を見える化する組織改革と、第一人者が語るリスキリング3.0時代』というFNNプライムオンラインに掲載されていたニュースですけれども、先生はどう思われますか?
(海老原)
誰がそんなことを語ったのですか?
(深田)
ジャパン・リスキリング・イニシアチブ代表理事の後藤宗明さんですね。
(海老原)
終わっていますね。
日本人は人事制度をまだほとんど理解できていません。おそらく、この方も理解していません。人事コンサルタントになっても10年ぐらい分からないのです。
(深田)
そうなんですか。スキルはそんなに簡単に分かるものではないのですか?
(海老原)
まずは面接したり、職務経歴書を書かせたりしますが、キャリアコンサルタントが、たとえばSEの経験者に「どんなシステムを担当していたのか」「どのくらいの工数で」「何人のチームで」「どういう手順でやったのか」といった質問を重ねて、ようやく「この人のスキルはこのレベルだな」と判断していく。なかなか分かるものではないです。
ですが、それ以前にスキルベースが人事制度として成り立たないということに気づいていません。
(深田)
人事制度としても、成り立たないのですか?
(海老原)
人事制度は「能力がどれぐらいあるのかを測ること」と「この仕事はどのような作業をやるべきか」の2つあります。ジョブ型は、この仕事はどういう仕事なのか細かく書いてあり「この仕事をやってください」というものです。
(深田)
企業が「どんな仕事をしてほしいのか」をはっきり認識していて、ジョブディスクリプション(職務記述書)も明確になっているということですか?
(海老原)
そういうことです。ただし、そこに問題が出てきます。欧米のジョブディスクリプション型は「仕事は何をやるか」から入っている。つまり「このポストは何をする」と細かく書いています。
そうなると2つの問題が生じます。1つ目は「それ以外の仕事が出てきた場合、誰がやるのか」ということです。たとえばコロナ禍で、オフィスに仕切りを設置する仕事が新たにできました。すると「ジョブディスクリプションに書いていないですよね(だからやりません)」と言われてしまうのです。
結局、欧米でも最近では、ジョブ型で細かい仕事を全部書くのは無理なので「この人はこのレベルの仕事をする」という“レベル表記”に変わりつつあります。つまり、具体的に何をするのか明確ではないということが1つ目の問題です。
(深田)
仕事内容ではなく“レベル感”だけで書いているのですか?
(海老原)
そうです。例えば「交通システムをメインにして100万工数ぐらいのものを開発し、部下は20人程度の仕事を任せます」といった具合の細かいタスクは書かないようになりました。日本はひと回り遅れて「ジョブ型だ」と言っていますが、欧米ではすでに細かく書かない方向に進んでいます。ここで認識のずれがあるわけです。
(深田)
えっ、もう欧米ではジョブをはっきり書かなくなっているのですか?
(海老原)
そうです。末端の人のジョブは細かく書いてあるというのですが、実際には「ここに書いていない仕事は上司の指示で行う」「空いている時間は隣の人を手伝う」とタスク管理ではなくなっています。タスクは細かく全部書いてある仕組みではなくなっているのです。
(深田)
欧米は“脱ジョブ型”に進んでいるのですね。
(海老原)
何をもってジョブ型と呼ぶのか、なので“脱ジョブ型”と言えるのかどうかですが「この仕事は何をやるのか」を書いているのが欧米型だと思ってください。そこが固定していると動かせないのが1個目の問題です。
では2個目の問題で「それはどのような人がやればいいのか」ということです。先ほどのような交通システムで100万ステップのシステム開発を、どんな能力を持つ人ならできるのか。任用条件が明確でなければ意味がなくなるのです。訳の分からない人を連れてきても「できません」というだけです。
(深田)
確かにそうですね。
(海老原)
そのため、任用条件がしっかり書かれていないといけないのです。これが『能力表記』になります。日本ではこれまで「この人はどんな能力を持っているのか」という人の能力を人事制度で管理する仕組みでやってきました。仕事の管理が抜けていたので、仕事の内容をきちん書くようにジョブ型がでてきたわけです。
一方、アメリカはその逆でした。ジョブはしっかりしていたものの、1980年代までは能力表記がほとんどなかったのです。そこで出てきたのが『コンピテンシー』(高い成果を出す人に共通する行動特性)の考え方です。しかし、コンピテンシーは人柄や行動のようなポータブルスキルばかり書いているので、実際にどのような技術が必要なのか、個別のタスクを解決できるのかなど個々のスキルが見えづらくなってしまった。そこで『スキルベースの人事』という発想が生まれたのです。
(深田)
なるほど。
(海老原)
とはいえ、能力や任用条件から入ると、また別の問題が出てきます。日本では「このランクに上がるには、こうした職業能力が必要」と定めていますが、それをクリアした人が「条件を満たしたが、仕事が規定されていないので、何もやらなくていいでしょう」と遊んでいる中高年年が増えたわけです。
(深田)
なんと!
(海老原)
つまり、能力ベースだけでは制度として機能しない。「このポストを担うには、この能力が必要」と定めても、具体的に何の仕事をするのか書かれていなければ、遊んでいてもいい状態になってしまう。だから、ジョブと能力の両方を明確にする仕組みが必要なのです。『その仕事はどんな能力が必要なのか』という任用条件と『この仕事の中身は何なのか』というジョブ要件の2つが揃って初めて人事制度として成立します。
(深田)
「仕事は何ですか?」と「それをできる人はこういう能力が必要です」という2つがセットですね?
(海老原)
そういうことです。さらに、「その能力を持っている人はどこにいるのか?」という課題もあります。
仮に僕であれば「話がうまい」「パワーポイントが作れる」「1年に数冊本を書ける」「テレビ出演にも慣れている」など、個人のスキルを一覧化しておく必要があります。そして「この仕事には、こういうスキルを持つ人が必要」となった時に、誰が最も適任なのかを判断することになりますが、こういうリスト管理が必要になってきます。
(深田)
それは、かなり大変ですね。
(海老原)
はい、大変です。「話が上手いからこの人をMCにしよう」と思っても、その仕事が1500万円規模であれば、そのスキルがあっても年収400万円の駆け出しの人に任せられるのかという問題があります。したがって、人格的・経験的なランクも考慮しなければならないのです。これらを全部合わせて人事制度なのです。スキルベースの人事は全体のごく一部にすぎないのです。全部が揃わないと無理なのです。
(深田)
それはそうですね。
(海老原)
次に「スキルベースで転職が進む」という話ですが、これも典型的なアメリカ型に対する誤解です。深田さんは、アメリカに詳しいから分かると思います。
(深田)
イギリスの会社に勤めた経験はありますが、アメリカでは仕事をしますが企業の中に入ったことがないので、あまりピンとはきません。
(海老原)
アメリカもイギリスもかなり似ています。深田さんがいた金融系のスペシャリスト企業は、どちらの国でも上位1〜2%の人たちの集団なのです。日本で言えば、東京の大手町で働くような層で、日本でもそのレベルで働ける人は全体の1%にも満たないです。
(深田)
確かにそうですね。
(海老原)
ですから、その1%の働き方を日本の働き方全部に当てはめるのは無理がある。アメリカの郵便局員は、ほぼ終身雇用で、給与もほとんど上がらないまま60歳まで働いています。日本では年功昇給があるけれど、アメリカでは「ポスト」に給与が紐づいています。そのポストの給与レンジが決まっていて、上限に達したらそれ以上は上がらないのです。
そう考えると、日本の方がまだましです。「職務」ではなく「職能等級」で給与が決まるため、同じ仕事でも等級が上がれば給料も上がるのです。車庫証明に印鑑を押すだけの仕事をしているおじさんがいますが、これはアルバイトでもできます。しかし、職能等級が高ければ高い給与をもらえるのです。
合理的なのは、アメリカのほうです。同じ仕事であれば、アルバイトのお姉さんと同じ給与しかもらえないようにしたほうが良いのに、高い能力を持っているというだけで、同じ仕事に高い給与を支払うのはおかしいです。
少し脱線しましたが、郵便配達や工場勤務といった職種では、ほとんど給与が上がりませんが、勤続年数は長いのです。ヨーロッパは長く勤める傾向があります。50歳の正社員男性の平均勤続年数は23〜24年ほどです。日本は21年です。
それに対してアングロサクソン系はよく辞めるといいますが、イギリスでも50歳男性の正社員の平均勤続年数は14年ほどです。アメリカやイギリスでも、ハイレベルな層では転職を繰り返しますが、一方で郵便局員や工場労働者のような層は、何十年も同じ職場で勤めています。
(深田)
それは、転職する先がないということですよね。
(海老原)
それを言えば、元も子もなくなりますが、そういうことです。
(深田)
金融機関は特殊で、花形プレーヤーになると、一人ひとりに年間の売上目標があり、達成度合いにより、ボーナスが決まります。業界の報酬は飲み会などで、情報を共有しているので、ボーナスに不満があれば「高いところに転職しよう」となってしまうのです。
(海老原)
そうでしょうね。ディーラーやキャピタリストのような人たちは確かに大きなお金を稼ぎますが、その代わり24時間働いていますよね。
(深田)
そうです。私も1日16時間ぐらい会社に拘束されていました。
(海老原)
そういう人たちは、だいたい最低でも50万ドルくらいは稼いでいるでしょう。彼らは40歳になるころには使い物にならないので、30代のうちに稼いで引退していく。しかも成績が悪ければ、すぐにクビを切られる世界ですよね。
(深田)
そうです。一瞬ですよ。振り返ったら、昨日までいた先輩がいなかったという状況でした。
(海老原)
そこですよ。アメリカで超高報酬の世界があるのは確かですが、日本人は、それが郵便局員にまで当てはまると誤解しているのです。
(深田)
そうですよね。それはごく一部の特殊な世界の話で、他の職場では労働組合が非常に強いですから。
(海老原)
ええ、特にヨーロッパでは組合の力が特に強く、アメリカもある程度強いです。確かにアメリカでは首切りが頻繁に行われていますが、その人は本当に仕事をしていません。普通のワーカーの中には、「それはクビになるだろう」という人が多いです。
たとえば、コールセンターの業務を在宅でやっている人が、電話が鳴っても出ない。上司が今日何件応対したの?」「これだけ?クビだ!」という事例がたくさんあるのです。そういう人たちが大量に存在していて、それがすべて混ざってのアメリカです。
(深田)
そうですよね。バラつきが大きいですよね。
(海老原)
スキルベースの働き方で、みんなが真剣に上を目指しているというのは、深田さんいたような業界だけです。
(深田)
多分、シリコンバレーやウォールストリートだけの話です。
(海老原)
その通り。スキルベースで動くのは、金融・IT・製薬業界ぐらいでしょう。あと不動産営業もフルコミッション(完全歩合制)だから、短期間でたくさん辞めます。つまり、アメリカはあらゆるタイプの働き方が混在しているのです。
(深田)
本当に格差がすごいですよね。
(海老原)
格差が日本とさらに違うのは、都市間格差が非常に大きいことです。たとえばシリコンバレーでは、初任給が1,000万円ぐらいですか。サンフランシスコの平均世帯年収は1,400万円ほどでニューヨークは850万円に下がり、デトロイトでは700万円程度です。
(深田)
でも、みんなが話題にするのはシリコンバレーやサンフランシスコばかりですよ。
(海老原)
本当にそうです。ニューヨークで「年収900万〜1,000万円が普通」と言われても、あの高い家賃と物価を考えたら、生活は地獄のようなものですよ。したがって「流行りに飛びつくのはやめましょう」というのが1つ目の結論です。
(深田)
「リスキリングして何とかしましょう」ということはいかがですか?
(海老原)
郵便局で働いていた人がリスキリングしてITエンジニアになれる訳がないでしょう。周辺領域にしか行けません。周辺領域から周辺領域に移るためのリスキリングはあります。
(深田)
周辺領域から周辺領域へ。それは具体的にどういうことですか?
(海老原)
たとえば、シーケンスを描く電気回路設計では、描くためのものがどんどん変化しています。以前は機械を動かすためのものが中心でしたが、今では画像認識やIT系のものなどに変わっています。その分野の変化に合わせてのリスキリングは、非常に効果的です。もともと電気や電子の基礎が分かっている人が、新しい技術の流れに合わせて学び直すことは『あり』です。
営業職でも、個人営業ではなく法人営業で、高額商品をチームで販売していた人がいるとします。そうした人が別の業界に移っても、商品知識を新たに身につければ、基本的なスキルはそのまま通用します。こういうリスキリングは『あり』です。しかし、未経験者がマシニングセンターを学んで職人になれるかと言えば、それは無理です。それと同じことですね。
(深田)
本当にそうなんですよ。仕事の相談を受けて、経歴を聞くと「軽作業しかしたことがない。パソコンは使ったことがない」という人が結構多いです。そうなると、シニア層の人には、紹介できる仕事がありません。
(海老原)
なぜそこまで何もせずにシニアになってしまったのか、そこを考えてしまいますね。
(深田)
その人はのんびりしていて、ハッピーな人なんですよ。ハッピーな人は、人生が少し厳しくても「将来どうしよう」と不安を感じないのですよね。
(海老原)
そうです。絶対にそれがいけないです。
(深田)
私は子どものころから『自分はこの国では自分は生き残れない』と思いながら生きてきたタイプです。
(海老原)
そこですよ。自己肯定感は大切ですが、強すぎるのも問題なのです。
(深田)
同感です。一緒に仕事していて一番困るのが、自己評価が高い人です。
(海老原)
根拠のない自信を持っている人がいますよね。僕は長年、ライターや編集の仕事をしていますが、文章の上手い新聞記者や、たくさん本を出している著者と飲んでいるとき、よく「どうすれば文章が上手くなるか」という話をします。そのときに皆が口を揃えて「自分の文章は伝わっていないのではないか」「わかってもらえているだろうか」と言うのです。不安に思う人ほど上手くなります。逆に「俺の文章はすごい」と思っている人は、絶対に上達しません。
(深田)
よくわかります。コメント欄を見て「ああ、私の書いた文章はこう伝わってるんだ」とショックを受けることがありますよね。
(海老原)
それはとても大切なことです。若いころは毎日のように「あの時こう書けばよかった」「ああ言えばよかった」と反省していました。
(深田)
SNSのXを見ていると、「この文章をそのように解釈するとは、お前は読解力がない」という人がいますが、この態度では伸びませんよね。
(海老原)
伸びませんね。「私は偉い。お前が理解しろ」というのはだめです。どの分野でも同じです。営業の仕事でも「このお客、なんでわからないの?」と思ったら終わりです。「どこが伝わらなかったんだろう?」と振り返ることですよ。
(深田)
美人ほど、自分のことをブスだと思っている。『今日の自分、ここがダメだった』と反省する女性がいるじゃないですか。あれですよね。
(海老原)
…。(苦笑)それでいうと、あなたはどこがダメなんですか?
(深田)
いやいや、今日も完璧です。もう何も直すところがありません(笑)。
本日は雇用ジャーナリストの海老原嗣生先生に「ジョブ型雇用なんてクソくらえ!」というテーマでお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
(海老原)
今日は真面目に話しましたよ。
(深田)
そんなことないですよ。