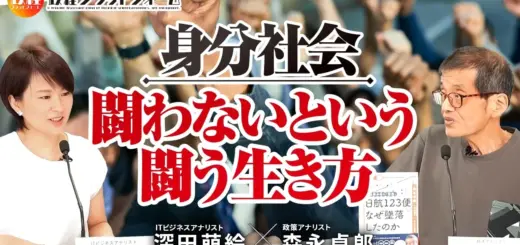子育て経費を減税しろ! 弁護士団が国税局と闘い始めた!? 税法弁護士三木義一氏 #310

【目次】
00:00 1. オープニング
00:40 2. 保育料は「経費?」ある弁護士夫婦の裁判事例
03:49 3. なぜ給与所得者は声を出さないのか? 必要経費控除の仕組み
04:47 4. サラリーマンが必要経費の実額を控除できない理由:年末調整
11:23 5. 必要経費の税法上の解釈
14:30 6. 判例の「一般化」を封じ込んでいる税務署
15:25 7. 税制改正の提言と今後の展望
(深田)
皆さん、こんにちは。政経プラットフォーム、ITビジネスアナリストの深田萌絵です。今回は、税法を専門とされている弁護士の三木義一先生にお越しいただきました。先生、よろしくお願いします。
女性の活躍推進を応援してくださっている三木先生からの素晴らしいご提言があるそうです。現在の国の方針としては、保育料を経費として認めてくれていないのですね。
(三木)
働くためには子どもを保育施設に預け、保育料を支払わなければなりません。そのため、これは収入を得るための必要経費性が強いはずなのです。
ところが税務署は未だに「それは家事費だ。家で奥さんがやるべきことだ」として認めていません。
実際にある共働きの弁護士夫婦が保育所に子供を預けなければならないので、保育料を経費として申告したところ、税務署から「これは認められません」と否認されました。そこで、その弁護士たちは今回、裁判で争うことにしたのです。
おかしいと思いませんか?
(深田)
おかしいですよ。国は「女性の活躍推進」を打ち出して「女性に働いてください」と言っています。それは「家事や子育てはアウトソースして、君たちはお金を稼ぎなさい」という意味になります。だったらアウトソースした分は外注費だから経費ではないのでしょうか。
(三木)
おっしゃる通りです。ただ、その問題意識が日本の場合はなぜかあまりこれまでも強く出て来ませんでした。
というのも、多くの働く女性たちは給与所得者です。だから必要経費を自ら実額で控除することをしていません。
(深田)
サラリーマンの着るスーツは経費になるのですよね?
(三木)
給与収入を得るために必要性があれば、当然経費だと私は思います。ですが税務署は「別にあなたがそれを着てもサラリーが上がるわけではないでしょう?」と言って、収入には関係ないとして、伝統的にはダメだと言ってきたわけです。
ただし、例外的に認めるのは例えばアナウンサーさんとか、テレビに出る俳優さんとかです。仕事でしか着られないような派手派手なモノは経費だけど、家で着られるものダメだという扱いを前提として来ました。
そうした狭い考え方のままなのですが、それに対する皆さんの怒りが未だに大きくないのは、多くの人は給与所得者だから、自分で経費を引くことをしないからです。
(深田)
その発想がお勤めのサラリーマン側にないのですね。
(三木)
夫婦共稼ぎならば保育料を払っているわけでしょう。本来、これは経費ですよね。だけどサラリーマンだと「給与所得控除」というものしかないから、自分の実際かかった経費を引くという訓練を受けたことがないわけです。だからみんな分からないのです。
一方で、弁護士は給与所得者でなくて事業所得者であり、且つ保育所へは働いている人しか預けられませんから、当然「働くことに伴う経費だ」として、今回ようやく申告したのです。
この問題を提起した時に、若い弁護士さんたちはみんな「そうだそうだ」と賛同して争う姿勢を示して、多くの賛同者も来たそうです。しかし、誰かが「税務署と争うの?税務調査があったら困るね」と言ったらしくて、そしたらみんな「それは怖い」とか言って一気に引いてしまったようです。弁護士でも怖がってしまうのです。
ですが、昔の「片稼ぎ」という世帯の仕組みから、今は明らかに「共稼ぎ」になっているわけです。ですから、サラリーマンも事業所得者も、子供を預ける人は皆経費だという意識を共有して、必要経費の範囲をきちんと認めさせていかないといけないと思っています。
(深田)
本当にそうですよ。その論法でいくと、忙しい女性はハウスキーパーさんやベビーシッターさんを雇わないと自分の家庭を支えられないですよね。
(三木)
日本の場合は、そうした人たちのほとんどが給与所得者なのだと思うのです。大手の会社に雇用されて偉い役職に着くのだけれど、給与所得者だからそういうものを引ける仕組みがないのです。だから声が上がらなかったわけです。これがやはりおかしいのです。
(深田)
「給与所得控除」はいくらでしたか?
(三木)
65万円です。
サラリーマンの人は、なぜ自分の収入にかかった経費を引けないのだと思いますか?
(深田)
どうしてですか?
(三木)
これは簡単な話です。日本では年末に、会社に「年末調整」をさせるでしょう?会社が全部やってくれます。そして皆さんには「確定申告しないでいいですよ」という風にしているわけです。
そして会社が「年末調整」をしようとする時に、Aさんの収入は分かる。Bさんの収入も分かる。でもみんなの必要経費の実際の額をそこで計算して調整しなくてはいけなくなったら会社の経理は大変です。そこで、会社が簡単に「年末調整」をできるように、収入金額から自動的に引ける経費の金額を決めてしまうという仕組みにしたわけです。
昭和22年、日本に確定申告の仕組みが入った時からこうしたのです。
(深田)
これにはGHQは関係あるのですか?
(三木)
GHQは確定申告をさせたかったわけです。
(深田)
GHQは確定申告をさせたかったのですね!
(三木)
大蔵省は最後まで徹底抗戦をしたのだけど、やはり当時はすごくGHQが強いから、GHQ は「アメリカの申告制度がいい。納税者としての自覚を持つために、日本もそういう制度が必要だ」として導入させたのです。
そしたら大蔵省が最後の抵抗で、11月くらいにパッと「年末調整」を入れたのです。それで日本の納税者の9割ぐらいは確定申告をしないで済むようにしてしまったのです。
(深田)
確定申告をしないので、日本人は「自分が払った税金が適正に使われているかどうか」という意識がものすごく低いと言われていますよね。
(三木)
だから納税意識も低いし、税の仕組みがよく分からないしで、税金のことがすごく嫌いなのです。その一方で、「保険料のことは全く分からない」という変な国民になっております。
(深田)
「年末調整」という名の愚民化政策だったのですね。
ところで、諸外国では保育料やベビーシッター代は経費に認められているのですか?
(三木)
基本的に経費です。それ以前に、子育ては国家の政策として重要ですから、様々な所得控除や、あるいは税額控除の仕組みを作って、わざわざ必要経費なんて言わなくても済むようにしている国が多いと思います。
(深田)
そうですよね。
20年くらい前の記憶ですが、香港では働いている女性がすごく多くて、仕事の時にはハウスキーパーさん兼ベビーシッターさんのような人を雇っていました。その差額分しか稼げませんが、それでも香港の女性は働きたいから働いているのです。そして、その分は経費として認められるから税金も安くなるということも聞きました。
(三木)
それは当たり前ですよね。本当はそうすべきです。
日本の場合は未だに、基本的に「子育てなどは家庭で奥さんや、奥さんの親御さんがやるべきものだ」という発想でいるわけです。これが少子化の1つの原因でもあると思います。
(深田)
「女性の活躍推進」と言いながら、女性が働こうと思ったらベビーシッターさんやハウスキーパーさんを雇わないといけないですし、保育所にも普通に皆さん預けているのに、それを経費として認めないというのは、女性の活躍の足を引っ張る政策ですよね。
(三木)
日本の税法では、昭和18年に初めて配偶者のことを見るようにしました。「産めよ増やせよ」の政策として、配偶者がいれば少し面倒を見るようになったのです。
戦後に「扶養控除」と一緒にして、「配偶者控除」などにしてきました。だけど、基本的には世帯の中では「扶養者」としての位置付けなのです。
今はもう独立して女性も働かなくてはいけない時代でしょう?そうしたら子育て自体の経費も社会的な費用のはずです。そういうものをきちんと税でも見てかないといけない。
(深田)
税法上では、これはどのように解釈できるのですか?
(三木)
税法上は「必要経費の範囲とは何か」という問題です。法人と違って個人は私的な活動もあるので、今までの扱いでは基本的に「明確に事業のためでなければ全て家事費だ」と見る傾向がありました。すごく狭いわけです。
税務署は常に「この費用はあなたの事業に直接必要ですか?」と聞いてきます。「直接必要でなければダメです」と言ってくるわけです。でも法律にはそんなこと全然書いていません。
(『所得税法 第37条 必要経費』によれば)「売上原価」などは直接それに対応しなければなりませんが、「販売費」「管理費」「その他の費用」に関しては、事業に必要なものであれば経費なのです。
10年ぐらい前になりますが、仙台の弁護士さんから「弁護士会の副会長に立候補してほしい」と言われて、私は立候補しました。そして副会長に当選しました。
弁護士会で立候補すると、やはり費用もかかるわけです。そこで自分の事務所の経費の中から「立候補費用」、それから弁護士会の副会長になったから東京に出て色々と懇親もしないといけないので「懇親会の費用」、更に弁護士会の職員の人の慶弔があった時の「慶弔費」も新たに必要経費として入れたわけです。
そしたら税務署が来て、「これは先生の弁護士活動に直接関係がないですよね。弁護士の副会長になる、それは先生がお好きだからやったのでしょう?」
(深田)
そんな訳ないですよね!
(三木)
そういう発想で、この3つを全て否認してきたのです。
弁護士会にも「税制委員会」というのがあって、そこの副会長さんが僕らに、「こんなことでいいのか」と聞いてきたのです。「この機会に僕らはこれをやろう。本来の業務に必要だったらみんな経費なのだという発想でやりましょう」となり、争うことにしたのです。
地裁では、裁判官が昭和30年代の古い発想で判決を書いて、こちらは負けました。そこで、おかしいということをいろんな資料を出して争ったら、高裁では「別に直接だろうが間接だろうが関係ない」という風に言ってくれて勝ちました。そして最高裁も「そうだよ」と言ってくれたわけです。
(深田)
素晴らしい!
(三木)
だから、本当はもう状況は変わってなくてはいけないのです。
ところが、この時に記者会見をしたのですが、新聞記者たちがこういう質問をしてきたのです。「この事件は弁護士会の副会長さんの事件ですよね?」と。そして答える人が「そうです」と言ってしまったのです。
そうしたら、「弁護士会は特殊な世界」ということで、誰も記事にしなかったのです。
(深田)
ええっ!こんな重要なことを?
(三木)
税務署は「これは特殊な事案で、あれは弁護士会だけに適用できるのです。一般には関係ありません」と盛んに言うわけです。
だけど事業所得の必要経費とはもっと広い話なのです。業務に関わるものは全て経費として見なくてはいけないのです。
(深田)
だって子供を連れて会社へは行けないのですから、保育料は必要経費ですよ。
(三木)
そうです。だけど仕方がないから、個人事務所で従業員を雇って、従業員に子守りをさせるなんて人もいます。
ですが、こういうことをやらざるを得ないこと自体がおかしいですよね。国として子育てを本当に税制上配慮していないことに私にも怒りがあります。そして、なぜ今頃こんなことで争わなければいけないのか。
(深田)
そうですよね。「今こそ、女性の活躍を推進しようとしている日本政府は、保育料、ベビーシッター代、ハウスキーパー代を全部必要経費として認めてください」ということですね。
(三木)
そういうことです。
今、若い弁護士さんたちが「保育料は経費だ」ということを訴えて、裁判に取り組み出しました。インターネットなどを見ていただきますと出ておりますので、もし関心がありましたら応援してあげてほしいと思います。
(深田)
これは2025年、今年の2月か3月ですね。まだ始まったばかりなので、頑張ってもらいたいです。弁護士先生を応援したいと思います。
(三木)
ぜひお願いします。
これは別に弁護士さんだけの問題ではなくて、サラリーマンである皆さんの問題でもあると思います。今みたいにサラリーマンには経費を一切基本的に認めないような仕組み自体が日本の税制を歪めてしまっているのです。
皆さんはやはり主権者として、税金は自分で計算して、自分の経費は全部きちんと自分で引くようにしないとおかしいと思います。
だってよく考えてください。今のように一律の控除額しか認めないというのは、一生懸命に仕事のために支出している人も、何も支出しない人も同じ扱いだからです。だから皆さん直しましょうよ。
(深田)
直したいです。私はOLの時代も仕事のために大量に本を買って読んでいました。本を買ったりしない人より、本を買っている方が出費は多いわけじゃないですか。
(三木)
税務署は「あなた、それだけ資産が増えましたね」みたいな発想で見るのだろうね。
(深田)
捨てたら認めてくれますか?(笑)
給与所得の人間も、普通にもっと必要経費を認めてもらうべき範囲を広げて、女性がもっと働きやすくしてもらいたいです。それだけでなく、保育料やベビーシッター代が経費だったら、ご主人も助かりますよね。
(三木)
そうですよ。この裁判で、給与所得の人も事業所得の人も関係なく、必要経費の前にまず「子育てに費用をかけていれば、その分は何らかの形で引かせる」という仕組みを作りたいのです。
(深田)
それは少子化対策にもすごくいいですね!
(三木)
そういう風な税制にするように、皆さんも是非声をあげていただきたいと思います。よろしくお願いします!
(深田)
今回は、税法を専門とする弁護士の三木義一先生から、素晴らしい女性活躍推進策と、そして少子化対策をお話しいただきました。先生、どうもありがとうございました。