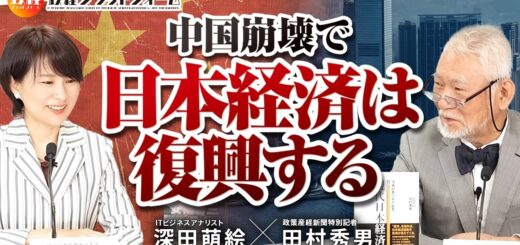消費税は単なるババ抜き? 知らなかった経済効果とは? 税理士・永井圭介氏 #290

【目次】
00:00 1. オープニング
00:38 2. インボイスでトラブル続出
04:18 3. 個人で仕事をしている人に`キツイ
07:15 4. 事務処理のトラブルが多発
11:24 5. 経過措置が無くなると消費税倒産
15:09 6. 消費税廃止が最高の政策
18:45 7. 大企業の少ない法人税納税
(深田)
皆さん、こんにちは。政経プラットフォーム、ITビジネスアナリストの深田萌絵です。今回は、税理士の永井圭介先生にお越しいただきました。永井先生よろしくお願いします。
前回は悲惨なお一人様の老後についてお話をいただきましたが、今回は、最近始まったインボイスでトラブルが続出していることについて教えていただけますでしょうか。
(永井)
前々から予想はされていたのですが、全く新しい制度なので、事務処理をどうすればいいかというところから、一番肝心な消費税分を、仕事を発注する側と受ける側のフリーランス、どちらが10%分を追加で負担するのかですね。そもそも、どういう対応をすればいいのか、全くそういうアイデアを国は示してくれていないまま始まったので、実務はいろいろ混乱しています。
(深田)
そうですよね。インボイスは、「国が税金二重取り、三重取りできる酷い仕組みだ」ということをおっしゃっている方もいます。課税事業者・免税事業者・課税事業者・免税事業者でサンドイッチすると、余分に税金を持っていかれているということだそうです。
(永井)
なるほどね。ただ正確に言うと重複はないのですけれども、今まで払わなくて良かった分を抜かれる構造になっています。スキップできていたところがスキップできなくなってしまったイメージでしょうか。
(深田)
具体的にどのようなトラブルがあるのでしょうか。
(永井)
そうですね、なんとなく制度が始まってしまったという人がほとんどだと思うのですね。我々税理士は研修で勉強して、クライアントにアドバイスしますし、逆にクライアントからの質問に答えているうちに理解が深まって、実務側はなんとか乗り切ってはいます。
しかし、全くわからないフリーランスの方、特に税理士をつけていない方ですね。大体売上1000万以下のフリーランスの方は、ほとんどつけていないと思います。なので、結局何をすればいいかわからないまま、例えば仕事を発注する側から一方的に、「来月からインボイス制度始まるので10%ディスカウントしてもらえますか」などと言われるのです。
フリーランスにとっては10%でもかなり大きいので、「いきなりそんなこと言われても」となりますよね。それなら仕事はしないと言える人ならいいのですが、言えない人が多いですから。要は誰がやっても同じような代替可能な仕事の人は、やはり、いきなり値下げされるけれど取引は切れないですね。
(深田)
ライターなどは一番厳しいですよね。
(永井)
よほどネームバリューがある方でないと、依頼する側の例えば出版社なども、「この人、うるさいこと言っているから他の人にしようかな。」とか、「この人はちゃんとインボイス登録すると言っているから、こちらに発注しようかな」という発想になりますよね。
(深田)
かわいそうだけれど、これ消費税のババ抜きになっていますよね、
私もいろいろなところに、お仕事をお願いする側なのですけれど、やはりインボイス登録していない人が結構多いのですよ。出演者さんもインボイス登録していない人が結構いらっしゃいます。そういう方はテレビに出ていたりしてネームバリューがあるので、おそらくあまりインボイスの影響がない方なのでしょうけれど、もしかしたら他のライターさんやサムネイルを作ってくれている方などは、煽りを受けているのではないでしょうか。
(永井)
あと多いのがパーソナルトレーナーやヨガインストラクターの方などですね。フリーランスが多いので。
(深田)
トレーナーでも年収200万円くらいの人もすごく多いですよね。中堅で500万円くらい。1000万円稼いでいるような人はほとんどいないので、そこから10%持っていくのは残酷だと思います。
(永井)
正確に言うと、自分も経費を使えばその分の消費税は引けるのですが、フリーランスの方はまともにやっていると経費はないので、結局10%近い消費税を負担することになってしまいます。
(深田)
フリーランスの方は自分の体1つでやっているから、消費税を引かれるような仕入れとかはないですものね。そういう人は大変ですよね。
(永井)
なので、国の方も考えていまして、いきなり10%まるまる負担することはないようになっています。売上1000万以下の事業者は、最初の3年間は2%の負担、それを過ぎたら本運用に移行します。少しずつ引き上げていく財務省の常套手段ですよね。
(深田)
いきなり引き上げたら百姓一揆が起こるので、じわじわと茹でガエルにする保身のための対策だと私は思っています。
他にも、もっといろいろなトラブルがありますか?
(永井)
あとは実務的なトラブルでしょうか。細かい話で言うと、領収書をどう書いたらいいのかです。そもそも国税庁の説明が少し分かりにくい。一応ひな型はありますが、八百屋だかスーパーだかの事例しかなくて、ライターやライターに発注する側がどう請求書を作ればいいのか例示がないので、「うちはどうすればいいの?」ということが多いですね。
(深田)
私も、「インボイス付きの領収書をください」と言われたことがあります。とりあえず領収書にインボイス番号を書いてみたのですが、これでいいのかな?と思いました。
(永井)
それで実務的にはもう80点です。T+13桁の番号を書けばいいのです。
(深田)
80点取れました(笑)
私の直感は正しかった。法人番号を調べて、それにTをつけました。
(永井)
法人の場合は、法人番号がそのままが流用されます。
正確に言うと、これは元々請求書・領収書に載っていますが、「消費税額をきちんと書いてください」というのがあります。インボイス制度が始まる前は、「税込みいくら」で良かったのです。
少し細かいルールがあって、「これがルールです」と言われると、「これがないと消費税が引けないのですか?」と変に警戒してしまってギクシャクするような、地味ですが事務処理上のトラブルも非常に多いです。
(深田)
そうですよね。私も、講演会費は税込なのですが、2000円の講演会で「インボイス付きの領収書をください」と言われた時に番号だけ書いて渡したら、「きちんと税金を書いてください」と言われました。
(永井)
きちんとしているところですね、それは。
(深田)
2000円の税金はいくら?となりました(笑)
小数点みたいになってしまうのですよね。これでいいのか?となりました。
(永井)
それでいいと思います。分かるようにしてればいいのです。
正確に言うと切り捨てをすればいいのですよ。
(深田)
切り捨てたら今度は1円足りないとかになりますよね。
(永井)
正直実務上は、端数はどちらに寄せてもいいのかなというのはありますね。
(深田)
そこは、税務署は突っ込んで来ないのですね?
(永井)
私は税務調査で言われたことはないです。そこは安心してください。
だけど、そもそも2000円を割り返すというのが…うーんという感じですね。今までは無視して良かったのですけれど。
(深田)
そうなのですよ。「2000円の消費税…うーん」ってなりますよ。でも2200円とかにするのも何か違うと思います。もし、2200円にすると、今度は当日来た人たちが「2200円だから3000円出します」となったら、お釣りの100円玉地獄が待っているわけですよ(笑)
そう思うと1000円、2000円、3000円という切りの良い数字でやりたいなと思う一方、「領収書下さい」と言われた時に「消費税の計算…」となります。他には、何かありますか?
(永井)
細かいことを言うといろいろありますよね。値下げ要求や取引を打ち切るというのが大前提で、それに対して独占禁止法が網をかけて、「こういう事例はダメですよ」というのが結構詳しくあります。「買いたたきはダメ」、「一回契約するって言ってやめたらダメ」などですね。
逆に、仕事を発注する側はとても神経質になっています。現にインボイス制度が始まったあたりに、「こういう業者がこういう行為を行いました」と国から発表されまして、吊し上げでやったわけですよ。
普通にやっていればいいのです。きちんと交渉して「じゃあお互い5%ずつ負担しましょうね」でもいいと思います。そういうのをやる前から「なんか怖いな、交渉すらやっちゃいけないの?」、「それならもうこっちで負担するしかないね」となって、結局その発注する側の税負担が増えるので、業績は下がりますよね。